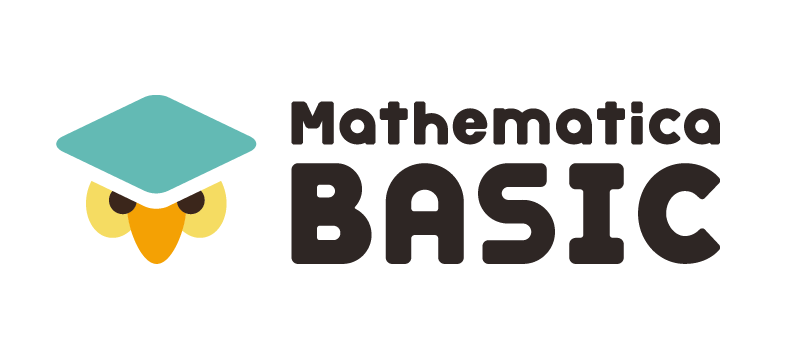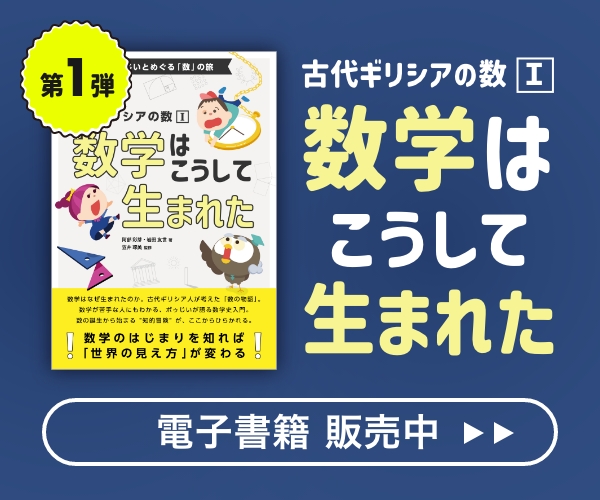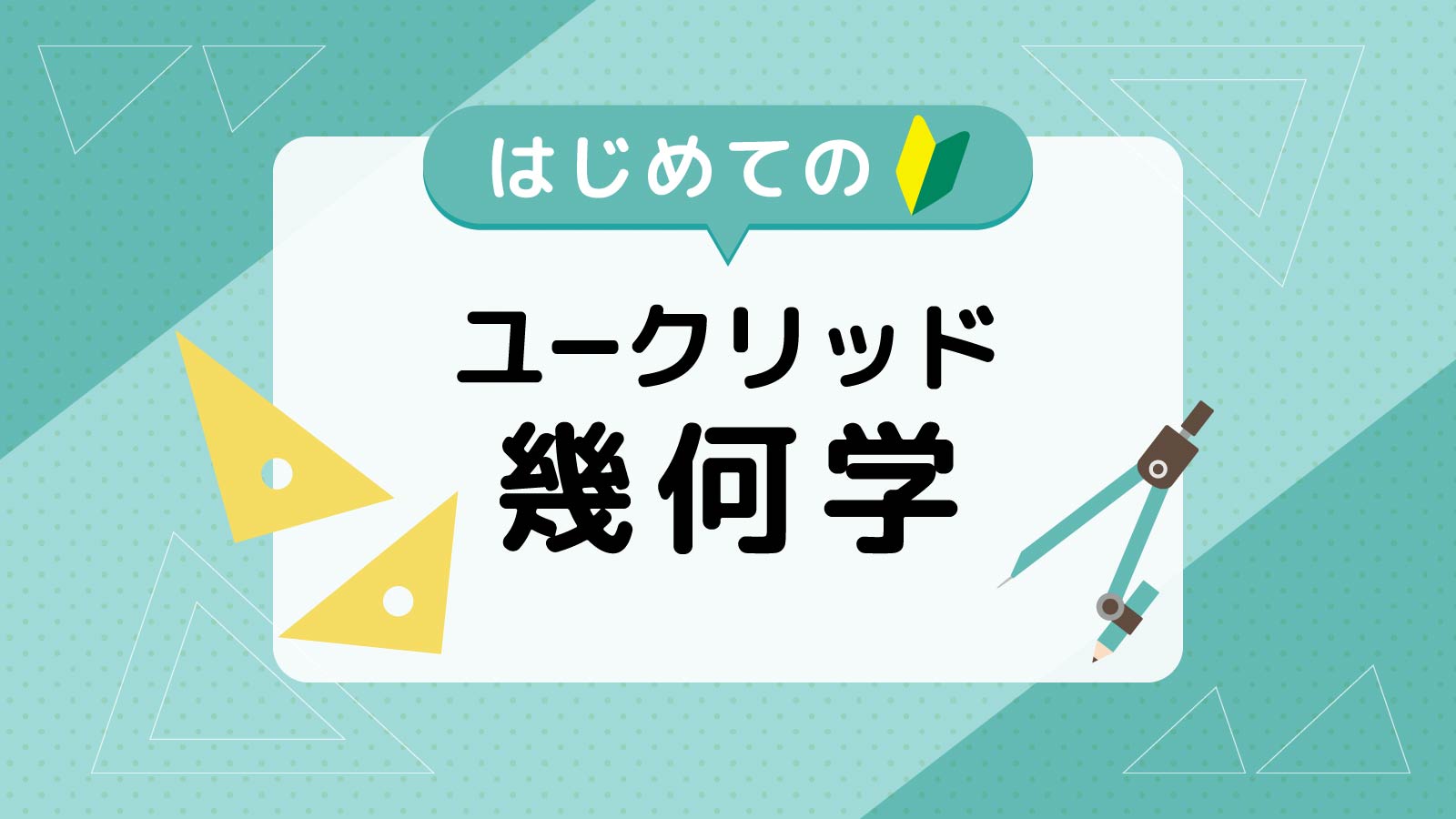
STEP3
幾何学の教科書 原論
古代ギリシアのユークリッドがまとめた数学書『原論』は、2000年以上にわたり読み継がれ、のちの数学に大きな影響を与えました。いまもなお“知の源流”として輝き続ける『原論』の魅力をひもといてみましょう。
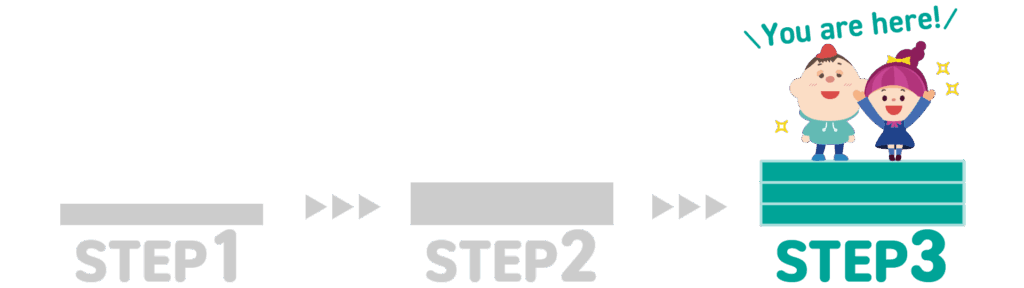

博士、ユークリッドが書いた数学書『原論』って、どんなことが書かれているんですか? 当時の人たちがどうやって数学を考えていたのか、もっと知りたいです。
うん…。古代ギリシアに書かれた本ってどんな本なのかイメージが湧かなくて…。学校で習う数学とつながりがあるのかどうかも、まだピンときてないです。


ふふ、ちょうどよい機会じゃの。『原論』はな、数学の基礎を組み立てた“教科書の元祖”のようなものなんじゃ。その中身について、もう少し詳しく紹介していこうかの。
ユークリッドの原論とは?
古代ギリシアのユークリッドがまとめた『原論』は古代ギリシア数学の集大成ともいえる大書です。
『原論』は、全13巻からなり、幾何学・数論・比などを体系的にまとめた「数学史上もっとも有名な本」と言ってよいでしょう。その影響は絶大で、ヨーロッパでは中世から近世にかけて、多くの数学者がこの本で幾何学を学びました。また長い間、大学の教科書としても使われ続けました。「聖書以外で、世界中でもっとも多く読まれた書物」と称されることもあります。
ユークリッドがこの書物の中で構築した幾何学の体系は、のちに「ユークリッド幾何学」と呼ばれるようになります。幾何学とは、図形や空間の性質を論理的に扱う数学の分野であり、『原論』はその出発点を築いた不朽の一冊といえるでしょう。

へぇ〜。紀元前に書かれた本なのに、近世まで大学の教科書として使われていたんですね!そんなに長い間読まれていた本があるなんて、なんだか歴史の重みを感じますね!
しかも“聖書以外でいちばん読まれた”なんて、すごいなあ…。どれだけ多くの人が幾何学を学んできたんだろう。


うむ、それほどまでに『原論』が大きな影響を与えたということじゃ。古代ギリシアの幾何学の考え方は、この本を通じて時代を超えて受け継がれてきたのじゃよ。せっかくじゃから原論についてもう少し見てみるとしよう。
原論の構成
『原論』は全13章からなり、主な内容は以下の通りです。
平面幾何(平面図形の基礎、面積、円、円と多角形)
比の理論(量の比、相似、数の比)
比と数論(連比、素数の完全数、非共測量)
立体幾何学(空間図形の基礎、面積と体積、正多面体)
平面図形の基礎である第I巻は次の定義から始まります。
定義1 点とは部分を持たないものである。
定義2 線とは幅のない長さである。
定義3 線の端は点である
…
定義のあとには5つの公準と9つの公理が続きます。公準と公理は命題を証明するための基本ルールのことで、いわば「誰もが認める出発点」 です。ここは証明せず、そのまま正しいものとして扱います。
簡単に言うと、『原論』では、言葉をはっきり定義する → みんなが納得できる前提(公理・公準)を置く → その上で筋道立てて命題を証明する、という順番で話を進めます。この進め方こそ、現代の数学がお手本にしている基本スタイルなのです。
古代ギリシアの量の捉え方
古代ギリシアの人たちは、「数」と「量」をはっきり区別していました。彼らにとって「数」とは、1, 2, 3, …といった自然数のことで、ものを数えるためのものでした。一方、長さ、面積、体積、角度などは「量」として捉えられていました。そして、それぞれの量は「同じ種類のもの同士」でしか「足し引き」や比較ができない、という原則があります。これが、ギリシア数学の大きな特徴です。
古代ギリシア人はこうした量の本質に深く迫ろうとし、そのうえで整然とした幾何学の体系を築きました。『原論』には、こうした基本的な量の性質が明確に示されいます。

私たちが習っている数学って、ユークリッドが活躍していた古代ギリシアから繋がっていたんですね!
数と量を区別して考えたり、今の数学とはちょっと違うようだけど…。合同の扱い方をきちんと決めたり、考え方そのものを大事にしていたんだなあ。


まさにその通りじゃ。ギリシア人は“ものごとをどう定義し、どう証明するか”を徹底して考えた。そうして築かれた幾何学の体系が、いまもわしらの数学の土台となっておるのじゃよ。
ユークリッドクイズ
ユークリッドは、紀元前300年頃にアレクサンドリアで活躍した古代ギリシアの数学者で、『原論』を著した人物として有名です。
Q
ユークリッドと同じ時代に活躍した数学者は次のうち誰でしょう?
1. アルキメデス
2. ニュートン
3. ガウス
答えを見る
A
アルキメデス
ユークリッドが活躍したのは古代ギリシアのヘレニズム時代と呼ばれる時代です。ニュートンは世紀、ガウス世紀の数学者。
この3人は世界三大数学者とされています。
Q
ユークリッドの時代、アレクサンドリアにあった「ムセイオン」という施設は、現代のある施設の語源になりました。それは何でしょう?
答えを見る
A
Museum(博物館・美術館)
ムセイオンは王立の学術研究所と、その付属の大図書館で、研究・教育・学芸活動の中心となっていました。ギリシア語 Mouseion がラテン語 Museum へと引き継がれ、やがて現代の Museum(ミュージアム=博物館・美術館) の語源となりました。
数学書クイズ
ユークリッドが著した『原論』は、後の数学者たちに大きな影響を与えてきました。当時の数学を後世に伝える数学書は、数学の発展に重要な役割を果たしています。
Q
ユークリッドの『原論』は、ヨーロッパで長い間数学の教科書として使われてきました。その期間はどのくらいでしょう?
A. 約100年
B. 約200年
C. 約2000年
答えを見る
A
C. 約2000年
近世まで幾何学の標準教科書として読み継がれました。聖書以外で、もっとも読まれた本と言われています。
Q
ユークリッドの原論以外にも、過去の数学を伝える古代の数学書がたくさんあります。古代エジプトで書かれた「リンド・パピルス」は、どのような内容を記した数学書でしょう?
答えを見る
A
古代エジプトの数学の問題集
リンド・パピルスは古代エジプトのアーメスという書記官が書いた数学書で、「アーメス•パピルス」と呼ばれることもあります。数学の例題と解答が収められています。
『はじめてのユークリッド幾何学』はこれで終了です!

長い年月を超えて読み継がれた『原論』。図形や数の性質を、一歩ずつ論理で積み上げていく姿勢は、今も変わらず大切にされています。『原論』を知ることは、私たちが学んでいる数学の土台を知ることにもつながるのです。
\ Mathematicaでは電子書籍を販売しています /
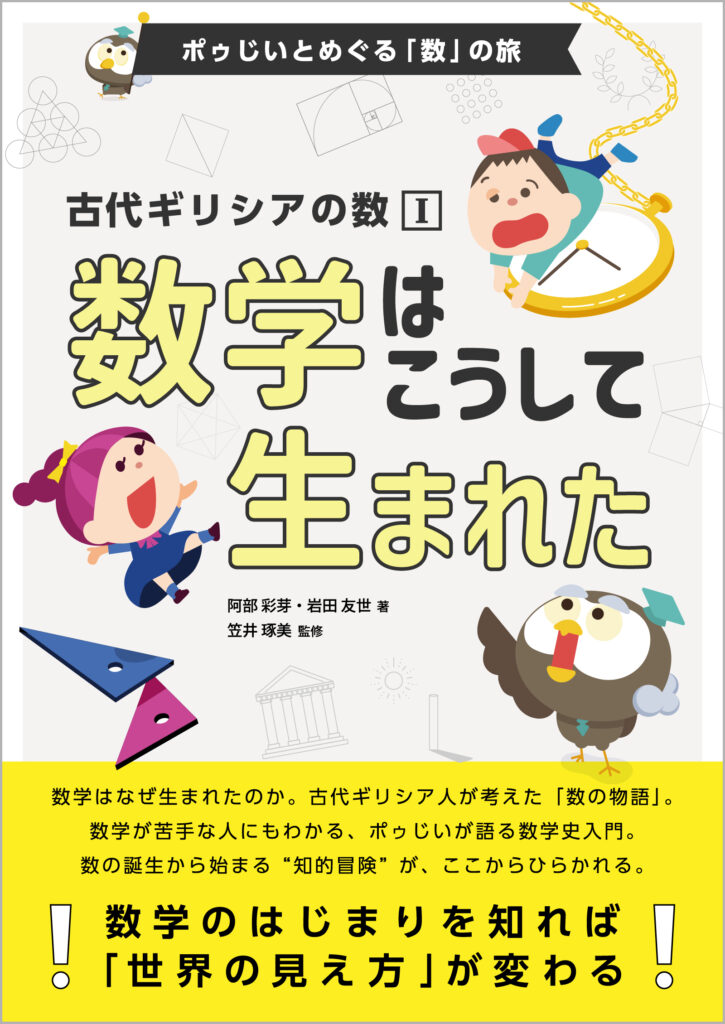
ポゥじいとめぐる『数』の旅 シリーズ
ポゥじいとめぐる『数』の旅シリーズは、数学史を対話形式でわかりやすく解説した電子書籍です。中高生の学びから、大人の知的好奇心まで幅広く応える入門書。数の歴史や発見の物語を、やさしく楽しくお届けします。
チャプター
Step1 . 三角形の合同・相似から学ぶ!図形の基本
– 三角形の合同条件
– 三角形の相似条件
– 幾何学と古代ギリシア
Step2. 幾何学の父ユークリッドとは?
– ユークリッドとはどんな人?
– ユークリッドが活躍した時代
– 学問は何の役に立つ?
– 幾何学に王道なし
Step3. 幾何学の教科書 原論
– ユークリッドの原論とは?
– 原論の構成
– 古代ギリシアの量の捉え方
– ユークリッドクイズ
– 数学書クイズ
キャラクター紹介

ポゥじい
Pou-Ji
フクロウの博士。数学のことならなんでも知っているけど、ちょっぴりうっかり屋さん。口ぐせは「学ぶって最高に楽しいんじゃよ!」

スウカ
数花
数学が得意な中学生。しっかり者で好奇心旺盛。歴史の知識も豊富でクイズが得意。数学の謎を見つけると目をキラキラさせる。時々鋭い指摘をする。口ぐせは「うんうん、わかってきたかも!」

カズオ
数男
数学はちょっと苦手な中学生。最近数学の面白さに気づいて学び始めた。のんびりマイペース。じっくり考える力はピカイチ。口ぐせは「よくわかんないけど、なんかおもしろそう!」